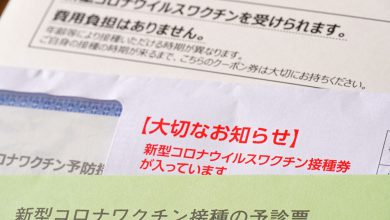新型の風邪「COVID-19」が露わにしたもの
ルポライター・明石昇二郎
まずは首相こそ冷静になろう
「過剰に反応する必要はない」
そう語る感染症専門家のコメントを、新聞やテレビが挙(こぞ)って取り上げていたのは、つい1か月ほど前の2月上旬のこと。そのたった1か月後に、「全国一斉休校」や「中国と韓国からの入国制限」といった過剰な反応を政府が次々と乱発していく事態が待ち受けていようとは、一体どれほどの人が予想できただろう。
首相官邸が「全国一斉休校」措置を実施するに当たって参考にしたのはおそらく、WHO(世界保健機構)が2月下旬に出したレポート「コロナウイルス疾患2019(COVID-19)に関するWHO-中国合同ミッション報告書」の中にある、
「感染の連鎖を遮断するためのより厳格な措置(大規模集会の中止、学校や職場の閉鎖など)を必要に応じて講じるために、多部門によるシナリオ・プランニングとシミュレーションを実施する」(翻訳はNPO法人 市民科学研究室による)
という文言だと思われる。だが我が国は、シナリオ作りやシミュレーションをすっ飛ばし、前触れもなくいきなり全国一律の一斉休校へと踏み込んでしまった。それで、国を挙げての大混乱に陥ったのである。1月下旬の春節(旧正月)の休みに1人の訪日中国人観光客も訪れることのなかった離島にある小学校くらいは休校措置から外すとか、少しは冷静に考えればよかったのに、と思う。
首相官邸が率先して浮足立ち、動揺を露わにしてしまえば、人々がそれと足並みを揃えて過剰反応してしまうのは、無理からぬことである。だから、首相も貴方も皆、冷静さを取り戻してほしい。
新型コロナウイルスに対する政府のこうした対応が理にかなったものであり、「過剰反応」ではないと一般市民に理解してもらうためには、そうせざるを得ないと判断した科学的な根拠や合理的な理由を、政治家が自らの口で丁寧に説明していくほかない。専門家が思いのほか頼りにならないと思われている今、
「専門家会議がそう言っている」
というのが「科学的根拠」だと言うのなら、きっと大半の人に納得してもらえないだろう。その証拠に、いくら専門家が、
「マスクで感染は防げない」
と繰り返し言っても、ヒトはマスクを買いに走るのである。
修羅場だからこそ、私たち庶民も意識しておくべきことがある。動揺した貴方がマスクを買いだめすれば買いだめするほど、新型コロナウイルスに感染した人の口を塞ぐマスクが足りなくなり、延(ひ)いては貴方自身が新型コロナウイルスに感染する確率を確実にアップさせることにつながる。普段なら、誰でも気づくことである。
スーパーや薬局の店頭からマスクや消毒液が消えたのに続き、新型コロナ対策とは全く関係のないトイレットペーパーや納豆まで店頭から消えてしまっている。動揺した人々による過剰反応以外の何ものでもない。動揺していないその他の人々にしてみれば、普通に納豆を買うことができないのだから、迷惑なことこの上ない。そして、そんな庶民の模様を報道機関が上から目線で繰り返し取り上げることによって、世間の品薄感と不安感に、より拍車がかかる。そんな「ニュース」や「報道」は、もはや害悪でさえある。報道に携わる人々もいい加減、冷静さを取り戻す必要がある。
筆者にも迫っていた感染の危機
とはいえ、中国発の新型コロナウイルス感染症「COVID-19」(コビッド・ナインティーン)が世界中に蔓延し始めているのは、紛れもない事実である。頑なに「パンデミック」(世界規模の感染症大流行)と呼ぶのを拒んできたWHOも3月9日、
「パンデミックの脅威が非常に現実味を帯びてきた」(テドロス・アダノム事務局長)
と、ついに大流行を認めざるを得ない状況へと追い込まれている。その2日後の3月11日には、テドロス事務局長が「パンデミックとみなせる」と表明。患者の封じ込め策は世界各国で軒並み失敗し、新型コロナウイルスは流行の勢いを増し続け、世界同時株安を招くなど、今やその影響は世界経済の浮沈にまで及んでいる。
こうなると、新型コロナウイルス騒動と無縁で過ごすことは、どんな聖人君子であろうと、不可能だ。
象徴的なのは、米トランプ大統領やペンス副大統領も出席していた2月末の集会で、参加者の一人が新型コロナウイルスに感染していたことが今月に入って判明し、騒ぎになっていることだろう。米国大統領でさえ、感染の恐れがあったのだ。どうやら2月中には世界各地でほぼ同時に市中感染が始まっていたようである。ただ、私たちが気づかなかっただけで。
かく言う筆者自身にしても、同じその2月に、感染の機会(=感染者)が目前にまで迫っていた。もちろん、その事実がわかったのは後日のことである。
高齢の実母が体調を崩して入院し、2か月近くに及んだ治療を終え、自宅に帰る前にリハビリを兼ねて母が世話になる予定だった老健施設(介護老人保健施設)で、送迎ドライバーが新型コロナウイルスに感染していたことが判明したのだ。
どこの老健施設でも、入所する前には家族面談が設定される。その面談の日、問題の送迎ドライバー氏が症状を訴えつつ、勤務していたというのだ。そんなことなどわかるはずもなく、筆者は妻とともに面談に出向いていた。そして面談日から10日後、当の老健施設から電話があり、
「ウチの送迎ドライバーが新型コロナウイルスに感染したことが判明し、今日から1週間、施設が閉鎖されることになりました。申し訳ありません」
というのだった。その担当者は、完全に冷静さを失っていた。
都内の老健施設に勤める職員が新型コロナウイルスに感染したとの話は、報道を通じて知ってはいたが、まさかそれが、実母がこれから入所する予定の老健施設だったとは、夢にも思わなかった。報道では、施設名も市区町村名も伏せられていたからだ。
母が入所する前に発覚したから、まだよかったのかもしれない――とは思ったものの、問題は、施設閉鎖のため、母が退院できなくなってしまったことだった。前代未聞の事態に、老健施設の担当者ばかりか、母が入院していた病院の担当者もケアマネージャーもソーシャルワーカーも、揃って筆者に謝るばかりで、ちっとも埒が明かない。
そこで筆者は、自ら指示を飛ばすことにした。感染した送迎ドライバー氏が勤務していたのは、母が入所を予定していた老健施設だけだったことを確認した上で、まずは老健施設のソーシャルワーカー氏に対し、同じ医療法人が経営する別の老健施設を手配するよう指示。入院していた病院にも、予定どおり退院させることを伝え、事なきを得たのだった。
残る問題は、筆者や妻が感染していないか、である。唯一の救いは、花粉症予防のため、マスクをして家族面談に臨んでいたことだった。
老健施設に確認したところ、同施設内では他の職員などに感染は広がっておらず、筆者の面談相手だった職員たちも無事であるとのこと。面談日からすでに1か月が経ち、筆者も妻も体調を崩すこともないので、どうやら感染は免れたようだ。
景気高揚策を「訪日観光客」に頼る危険
新型コロナパニックは、この国に潜んでいたさまざまな弱点や欠陥を露わにしていた。
まずは、政府が唱える「水際対策」の脆さだ。
新型コロナウイルスを中国・武漢から日本国内に持ち込んだ観光客の中には、発熱や咳などの自覚症状はあったものの、市販の解熱剤を飲んだら症状が緩和したので来日したという人がいた。
空港の検疫所では「水際対策」として、37・5度以上の発熱を検知するサーモグラフィーを使って入国者を調べていた。しかし、解熱剤を飲んでいた新型コロナウイルス感染者は、サーモグラフィーによる検疫に引っかからず、素通りしてしまっていたのだ。つまり、解熱剤はサーモグラフィーを無効化する。
中国国内での感染拡大時期が春節の休みと重なり、普段以上に訪日観光客が多かったことも災いしているのだろう。「水際対策」が脆いままである限り、いくら国内で患者の封じ込め策が功を奏したとしても、新型コロナウイルスは訪日観光客に紛れ、繰り返しやってくる。春節に次ぐ訪日観光客ラッシュは、今夏に控える一大イベント・東京五輪あたりだろうか。となると、日本が次の感染ピークを迎えるのは、東京五輪の開催時か、その直後かもしれない。
ところで、外国人の訪日旅行(インバウンド)の増加を目指す日本政府のキャンペーン「ビジット・ジャパン」政策がスタートしたのは、中国南部の広東省を起源としたSARS(重症急性呼吸器症候群)が流行した2003年のことだ。この年の訪日中国人観光客数は44万人だったのが、2018年にはその20倍近い838万人にまで激増。その一部が感染していただけで、このたびの新型コロナウイルス禍が我が国へともたらされる結果と相成った。
何も日本に限らず、インバウンドに多くを期待し、観光立国を標榜している国々では、同様の事態が今後も繰り返し発生する可能性がある。観光立国ならではの弱点であり、いわば負の宿命とも言えるだろう。
商売でグローバル化を進めれば、感染症の流入を避けられないのは自明の理、なのである。
備えあれば、憂いなし…だったのに!
3月7日付『東京新聞』朝刊が報じていたが、安倍政権は観光を成長戦略の柱に位置付け、訪日外国人が増加したことを盛んにアピールする一方で、感染症対策の要である国立感染症研究所(感染研)の新規採用を抑制し、研究費も毎年削減を要求していたのだという。つまりは感染症対策を軽視していた。
今でこそ、安倍政権は感染研を重用し、政府の専門家会議でも感染研の脇田隆字所長が座長を務めている。
感染研の前身は国立予防衛生研究所(予研)。血液製剤を介して血友病患者にエイズ感染を広げた1980年代の「薬害エイズ」事件の際、海外から輸入される血液製剤に危険があるとの情報を掴んでいながら、当時の予研は看板に掲げた「予防衛生」の役目を何ら果たせず、看板倒れとの批判を浴びていた。
看板を掛けかえた感染研は今回、汚名を返上し、名誉を挽回できるのか。大いに期待がかかるところである。
そのためにも、研究者の数を増やすことをはじめとする感染症研究体制の増強と、研究費の確保が望まれる。ただ、その成果が上がるのは数年先の話であり、現在の「新型コロナウイルス対策」にはとても間に合いそうにない。いつ新たな〝殺人感染症〟が現れるかわからないのであれば、平時から備えておくほかなかったのである。
9年前の東京電力・福島第一原発事故の時と同様、政府や専門家でさえ事態をコントロールできないことが明らかになった時、国民の間でパニックが発生する。マスクから納豆に至るまでの買いだめ騒ぎが起きるのも、元はと言えば備えを怠った政府の責任によるところが大きい。
今回の新型コロナウイルス禍に懲りて、我が国の感染症対策は、ましなものへと変わっていくのだろう。貧弱なウイルスの検査体制や、脆さを露呈した「水際対策」にしても、多少は改善していくと思われる。
ただ、感染が収まった時、我が国の経済や文化、芸術、興行、スポーツ、観光等の各業界がどれほどダメージを受けているのか。存続が危ぶまれるようなことはないのか。想像するのも恐ろしいぐらいである。
「振り返ってみると、安倍政権は亡国の政権だった」
と言われぬよう、健闘を祈る。首相官邸が率先して浮足立っていることが明らかになった今、過度な期待などしてはいないけど。
「差別」が感染を水面下で広げる恐れも
身もふたもない言い方をしてしまえば、新型コロナウイルス感染症とは「新型の風邪」にすぎない。
余談だが、日本で新型コロナウイルス肺炎患者が確認され始めた頃、患者が発生した地域や医療機関の周辺で、患者や医療従事者を露骨に蔑視・差別し、「ばい菌」呼ばわりする言動が聞かれた。実は、筆者の実母が世話になる予定だった老健施設の周辺でも、そうした声を耳にしている。
だが、感染者や病気を蔑視したり敵視したりしたところで、感染が防げるわけでもない。しかも、誰もが「明日は我が身」となりえる。
それに、感染者や肺炎患者が全国各地で発生するに至って、今では日本の国が丸ごと蔑視される立場となった。海外では、日本人だというだけで「コロナ」呼ばわりされる人もいるという。「ばい菌」呼ばわりしていた人が海外に行けば、今度はその人が「コロナ」呼ばわりされる番なのだ。
感染症にまつわる差別や蔑視の問題は、政府や専門家、感染研がいくら奮闘したところで、解決は困難である。ハンセン病患者やその家族に対する差別の問題に世間の注目が集まり、解決策が打ち出されるまでに数十年もの年月がかかっていることを思うと、途方に暮れるばかりだ。今回の新型コロナウイルス禍でも、感染した患者に対するいじめや差別が蔓延(はびこ)り、検査を受けるのを躊躇(ためら)う人が続出するような風潮が生まれれば、患者の把握も困難になり、かえって感染が水面下で拡散し続けてしまうことにもなりかねない。
ハンセン病の差別撤廃に関する国連特別報告者のアリス・クルス氏が、調査を終えて2月19日、東京都内で記者会見した際、こう語ったのだという(『朝日新聞デジタル』2020年2月20日 14時00分より)。
「公衆衛生政策は社会を守るためのものであっても、個々人の人権を侵害してはならない」
胸に刻みたい言葉である。
【2020年3月14日執筆】