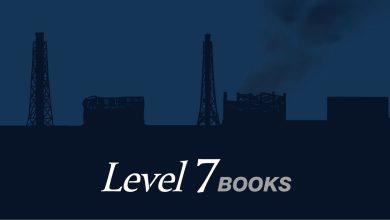第35回公判傍聴記

指定弁護士、禁錮5年を求刑
12月26日の第35回公判では、検察官役を務める指定弁護士が、勝俣恒久氏ら3人の被告人の罪について、これまでの公判での証言や集めてきた証拠をもとに論告[1]を読み上げた。事故がもたらした結果の大きさ、被告人の地位・立場・権限の大きさ、やるべきことをやっていない程度などから、業務上過失致死傷罪の中でも責任は極めて重いとして、3人に禁錮5年を求刑した。
論告・求刑は午前10時から休憩をはさんで午後5時すぎまで続いた。石田省三郎弁護士ら指定弁護士5人が交代しながら論告を読み、最後に「被告人らに有利に斟酌すべき事情は何ひとつない」「3名の責任の大きさに差をつける事情もない」として3人に同じ量刑を求めた。
論告の中では、これまでの公判では触れていなかった東電社員や原子力安全・保安院職員の供述調書についても述べられており、新たな事実もわかった。
キーワードは「情報収集義務」
10月に行われた被告人3人への本人尋問では、責任を転嫁する供述が目立った。
「特に津波についての問題意識はありませんでした」
「原子力部門のほうで自立的にやってくれるものだと思っていた」
「取扱を土木学会に検討依頼したい」
「まとまったところで報告があると思っていた」
指定弁護士は、こんな被告人らの責任を問うキーワードは「情報収集義務」であるとして、以下のように述べた。
「15.7mの津波計算結果などを契機に、被告人らが他者に物事を委ねることなく、自らその権限と責任において、積極的に情報を取得し、これらの情報に基づいて的確かつ具体的な対策を提起し、これを実行に移してさえいれば、本件のような世界に例をみない悲惨な重大事故を防ぐことができたのです」
担当社員は「対策必要」で一致していた
指定弁護士が細かく調べたのは、東電で津波想定を担当する土木調査グループ[2]の動きだ。酒井俊朗グループマネージャー(GM、第8、9回公判証人)、高尾誠課長(第5〜7回)、金戸俊道主任(第18、19回)と計7回の証人尋問を重ね、被告人らの責任を浮き彫りにしてきた。
指定弁護士は、こう述べた。
「土木調査グループが一貫して、長期評価を取り込んで津波評価を行う必要があると考え、大規模な津波対策工事が必要であると認識していたことについて、酒井、高尾、金戸の3人の証言は一致しています。そして、東京電力におけるメール、議事録、資料等にも、土木調査グループのこうした認識と方針が明確に示されています」[3]
「武藤被告人、2008年6月10日には対策の義務」
武藤氏には、吉田昌郎・原子力設備管理部長ら部下から、津波想定の結果や対策工事について、2008年6月10日と同年7月31日の両日に、具体的な進言がされていた。論告では、武藤氏の過失責任について「これらの努力を全く無視してしまったのは、武藤被告人自身に他なりません。このような事情にありながら、担当者からの報告がなかったとして、弁解し、自らの責任を回避しようというのは、責任転嫁も甚だしいといわなくてはなりません」とされた。
そして、2008年6月10日の時点で
①原子力設備管理部の担当者らに対して、具体的な津波対策をすみやかに検討させ
②その結果を勝俣氏や武黒氏らに報告するとともに
③常務会や取締役会を開いて、対策工事を実施することや、これが完了するまでは原発の運転を停止すべく決議するよう進言する
などの義務があったとした。
指定弁護士は、「その義務を怠り、それ以降も漫然と原発の運転を続けた過失があり、本件事故を引き起こした」と述べた。
「武黒被告人、2009年4月か5月、対策の義務」
武黒氏は、2009年4月か5月に、吉田・原子力設備管理部長から津波予測について報告を受けた。遅くともこの時点で、武藤氏が2008年6月10日時点で聞き知った内容と同じ事態を認識していた。当時、武黒氏は、原子力・立地本部長で、原発の安全について第一次的に責任を負う部署のトップだった。
論告では、報告を受けた時点で、
①担当者に具体的な津波対策を検討させ
②勝俣氏ら最高経営層に報告するとともに
③自ら、常務会や取締役会に対して、対策工事を実施することや、これが完了するまでは原発の運転を停止すべく決議するよう提案し
④これを実行する
義務があったし、「漫然と、部下からの報告を待つだけということなど許されないのです」と説明されている。
「勝俣被告人、疑問や不安を抱かなかったこと、おかしい」
勝俣氏は、「福島県沖については、津波は、基本的に大きな津波は来ないということで聞いていましたので、特に津波についての問題意識はありませんでした」と供述していた(第33回公判)。
一方、2009年2月11日の「御前会議」で、吉田部長から「もっと大きな14m程度の津波がくる可能性があるという人もいて、前提条件となる津波をどう考えるか、そこから整理する必要がある」という発言を聞いていた。
指定弁護士は、「吉田部長の発言に、何の疑問を抱かず、不安をも抱かなかったことこそ、おかしいのです。もし疑問も不安も抱かなかったとすれば、原子力発電所の安全性についての意識が著しく欠如していたということになります。最高経営層としての資格をも問われるものといわなくてはなりません」と指摘。「御前会議のもっとも上位の者つまり『御前』として出席し、同じ場には武黒氏、武藤氏、原子力設備管理部長など担当者もいたのだから、正にその場を活用して、丹念に報告を求め、綿密に協議し、他の被告人らとともに津波対策を検討すべき義務があった」と説明した。
初めて明らかにされた事実も
論告の中では、検察や指定弁護士が集めた関係者の供述や、電子メールや議事録も数多く示された。その中にはこれまで明らかにされていなかった内容もあった。
たとえば「御前会議」について、被告人らは、この会議が意思決定の場ではなかったと強調していたが、清水正孝元社長は異なる供述をしていた。
「『中越沖地震対応打合せ』(御前会議)のように、会長から発電所の所長に至るまで、これほどの幅広に集まって方向性の議論を行い、共通の認識を持つ場というものは、私が知る限り、これまで例がなかったと思います」
「『中越沖地震対応打合せ』は、常務会等で意思決定する前段階として、経営層の耳にいれておくべき中越沖地震後の対応に関する重要案件につき、情報を共有し合い、方向性の議論を行って、その方向性につき共通の認識を持つ場でした。その後、原子力・立地本部等の担当部署が、さらに、その方向性に基づいて、具体策を煮詰めていき、最終的には、常務会等において意思決定がなされることになります」
「御前会議」について、被告人らは「情報共有の会合であり、意思決定の場ではない」と繰り返し否定し続けていたが、実際には「方向性の議論と、その共通の認識を持つ場だった」と元社長が供述していたのだ。
東電の民事訴訟における主張、嘘とばれる
被害者らが東電を訴えている民事訴訟で、東電は「水密化や高所配置等の対策[4]は、本件事故を知っている今だからこそいえること」と主張している[5]。事故前には発想がなかった、後知恵だと言うわけだ。しかし、論告の中で、そのような対策を東電が事故前から検討、認識していたことが明確にされ、東電が嘘を言っていたことがわかった。
東電・機器耐震技術グループの長澤和幸氏は、第1回溢水勉強会[6]後の2006年2月15日に、「想定外津波に対する機器影響評価の計画について(案)」を作成。影響融和のための対策(例)として、進入経路の防水化、海水ポンプの水密化、電源の空冷化、さらなる外部電源の確保という具体的な対策を挙げていた[7]。事故の5年前に、すでに社員が作成した水密化等の報告書があったのだ。
また、2006年11月10日に開催された電事連既設影響WGで、各電力会社の津波対策が報告されていたこともわかった[8]。たとえば中部電力は、「原子炉建屋等の出入り口には腰部防水構造の防護扉等が設置されている」としていた。水密化対策に他社が取り組んでいることも、東電は知っていたことになる。
これらの事実は、政府や国会の事故調では報告されておらず、今回の公判で初めて明らかにされた。東京地検が収集した証拠や、指定弁護士が新たな捜査で得た証拠を集大成した論告を読み込むと、まだまだ同じような発見が期待できそうだ。刑事裁判が明らかにした事実は、東電や国の嘘や隠蔽を暴くことに役立ち、各地の民事訴訟にも大きく影響を与えそうである。
[1] 論告は、以下の構成で全194ページ。年表つき。
「はじめに」
第1「本件事故の経過と原因」
第2「被害の状況」
第3「被告人らの立場と『情報収集義務』の契機となる事実」
第4「地震対策センター土木調査グループの活動」
第5「長期評価の信頼性」
第6「結果回避義務の内容と結果回避可能性」
第7「被告人らの『情報収集義務』の懈怠と過失責任」
第8「情状」
http://kokuso-fukusimagenpatu.blogspot.com/2018/12/blog-post.html
[3] 論告p.26
[4] 敷地が水につかることを前提とした、ドライサイトにこだわらない対策
[5] たとえば、生業訴訟の被告東京電力最終準備書面(2)(責任論及び過失論について)2017年3月10日 p.86
[6] 原子力安全・保安院と原子力安全基盤機構(JNES)が開催していた、原発の津波に対するアクシデントマネジメントを検討する会合。
[7] 論告p.123
[8] 論告p.125



-390x220.jpg)