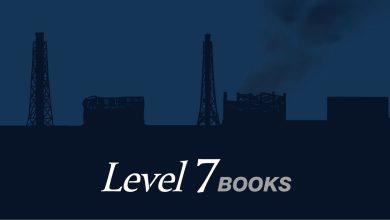第31回公判傍聴記
.jpg)
「Integrity(真摯さ)」を大切にしていた?
10月17日の第31回公判は、前日に引き続き武藤栄・元副社長の被告人質問だった。(今回の傍聴記では、30回、31回の2回の中で出てきた話が混在していることをお断りしておく)。武藤氏は「ISQO」(アイ・エス・キュー・オー)という言葉をたびたび持ち出して、自分の判断が正しかったと説明していた。
武藤氏によると、
Integrity(誠実さ、正直さ)
Safety(安全)
Quality(品質)
Output(成果)
の頭文字をつなげたのが「ISQO」。それを仕事では心がけていたのだそうだ。そして「Integrityに最も重きを置いていた、Outputは最後についてくるもので優先させてはいけない」と何度も強調した。
具体例として、発電所から「稼働率の明確な目標を示して欲しい」と声が上がったときに、数値目標をかかげることを自分の判断で却下した事例を武藤氏は法廷で紹介した。「Outputを目指すとどこかで勘違いする人がいるので認めませんでした」のだという。
経営の分野において有名なピーター・ドラッカーの『現代の経営』で、上田惇生氏はintegrityを「真摯(しんし)さ」と訳している。
人格や真摯さに欠ける者は、いかに知識があり才気があり仕事ができようとも、組織を腐敗させる。(『現代の経営』から)
=2011年3月、東電本社で。木野龍逸氏撮影.png)
「原発止めると大変な影響」
武藤氏は、原発を止めるのが、いかに「大ごと」なのか、以下のように説明した。
原発は東電の電力の4割近くを生み出す大きな電源なので、止めるとなれば代替を探してこなければならない。
火力しかない。その燃料を確保しなければならない。燃料を輸送する手当も必要だ。燃料費も一年に何千億円もかかる。火力は原子力より1kWhあたり10円ぐらい高くつくから、柏崎刈羽原発のように500億kWh生み出す原発を止めると、年に5000億円燃料代が余計にかかる。
そのお金を借りるなど、手当しなければならない。収支を企画や経理にも検討してもらう必要がある。顧客に負担してもらうことになれば、料金部門にも考えてもらうことになる。
送電線の中を電気が流れる「潮流」も大きく変わるので、電力系統の運用をやっている部門にも、系統の信頼性や安定性にどういう影響があるか見てもらわないといけない。
火力発電所を増やすと、二酸化炭素の排出が増えるので、その排出権の手当をする必要がある。
日本全体の3分の1が東電。東電の原発から電気を送っている東北電力など他の電力会社でも検討してもらわないといけない。また、東電が原発を止めるとなると、他社の原発は止めなくても大丈夫なのかともなる。それへの対応も検討してもらうことになる。
地元の自治体、資源エネルギー庁、原子力安全・保安院や原子力安全委員会にも説明して理解を得る必要がある。
だから「大変多くの部門に協力してもらわないといけない」とし、「止めることの根拠、必要性を説明することが必要です」と強調した。
この説明からは、Outputへの影響が多大だから、津波のリスクが確実でないと原発は止められないと武藤氏は考えていたように聞こえた。稼働率という数字を確保すること(Output)を、IntegrityやSafetyより上位に置いていたのではないだろうか。
本当のISQOに従えば、原発が事故を起こしたときの被害の大きさを考えると、津波予測に不確実な部分が残っていたとしても、その不確実さを潰すのに何年も費やすより、早めに予防的に対処するのが、真摯で安全な経営判断だったのではないだろうか。
最も安全意識の低かった東電
武藤氏は「地震本部の長期評価に、土木学会手法を覆して否定する知見は無かった」とも述べた。しかし反対に、土木学会手法に、長期評価を完全に否定できる根拠も無かった。
「土木学会手法は、そこ(福島沖)に波源を置かなくても安全なんだという民間規格になっていた。それと違う評価があったからと言って、それをとりこむことはできません」
武藤氏のこの陳述は、事実と異なる。他の電力会社は、土木学会手法が定めている波源以外も、津波想定に取り込んでいた。
東北電力は、土木学会手法にない貞観地震の波源を取り入れて津波高さを検討し、バックチェックの報告を作成していた。
中部電力は、南海トラフで土木学会手法を超える津波が起きる可能性を保安院から示され、敷地に侵入した津波への対策も進めていた。
日本原電は、東電が先送りした長期評価の波源にもとづく津波対策を進めていた。原電は「土木学会に検討してもらってからでないと対策に着手出来ない」と考えていなかったのだ。
「津波がこれまで起きていないところで発生すると考えるのは難しい」と武藤氏は述べた。これも間違っている。
2007年度には、福島第一原発から5キロの地点(浪江町請戸)で、土木学会手法による東電の想定を大きく超える津波の痕跡を、東北大学が見つけていた。土木学会手法の波源設定(2002)では説明できない大津波が、貞観津波(869年)など過去4千年間に5回も起きていたことを示す確実な証拠が、すでにあったのである。
土木学会が完全なものとは考えていなかった他社は、どんどん研究成果を取り入れて新しい波源を設定し、津波想定を更新していた。東電だけがそれをしなかった。Safetyのレベルは、電力会社の中で、東電が最も低かったことがわかる。
時間をかけて議論しても「安全」なのか
「知見と言ってもいろいろある。簡単に取り入れられるかどうかわからない」「現在でも社会通念上安全で、安全の積み増し、良いことをするのだから」
武藤氏はこのように、バックチェックに時間をかけても良いとも主張した。
確かに、新たな知見にもとづく津波を原発でも想定すべきかどうか確かめるのに、ある程度の時間は必要かもしれない。しかし、長期評価の津波予測については、東電は2002年8月に検討を要請されていた。それを事故が起きる2011年3月まで9年近く、ほぼ対策を取らないままの状態で、運転を続けていた。
原発が最新知見に照らし合わせても安全かどうか、運転しながらの確認作業について、規制当局は2006年当時、「2年から2年半以内で」と念押ししていた。なぜなら、安全を確認している期間中は、原発の安全性が保たれているという保証がないからだ。
しかし東電は、土木学会手法を超える津波の予測が次々と報告されていたにもかかわらず
「確率論的な方法で検討する」(2002年)
「土木学会で検討してもらう」(2008年)
「津波堆積物を自分たちで掘って確認する」(2009年)
など、いろいろな言い訳を持ち出して、想定見直し・対策着手を先延ばしし続けていた。
「記憶に無い」「読んでない」「説明を受けてない」の真摯さ
そういうことを考えながら傍聴していたので、「記憶にない」「説明を受けてない」「読んでない」と、自分の主張と矛盾する証拠類を否定し続ける武藤氏がIntegrityという単語を持ち出すたびに、「またか」と苦笑せざるをえなかった。
(第30回、31回公判の武藤被告人の傍聴記は、AERA2018年10月29日号[22日発売]にも2ページの記事を書いています。そちらもあわせてご覧ください)



-390x220.jpg)