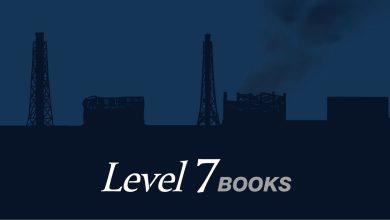第18回公判傍聴記

「津波対策は不可避」の認識で動いていた
6月20日の第18回公判の証人は、東京電力の金戸俊道氏だった。金戸氏は事故前、高尾誠氏(第5〜7回公判の証人)、酒井俊朗氏(第8、9回公判の証人)の部下として、本店土木調査グループで津波想定の実務を担当していた。現在は同グループのマネージャーだ。
検察官役の渋村晴子弁護士の質問に金戸氏が答える形で、土木調査グループと、実際の対策を担当する社内の他の部署や、他の電力会社とのやりとりの様子を、メールや議事録をもとに詳しくたどった。渋村弁護士は、会合一つ一つについて、出席者の所属や、彼らが出席した目的を説明するよう求め、「津波対策は不可避」という認識で東電社内が動いていたことを明らかにしていった。
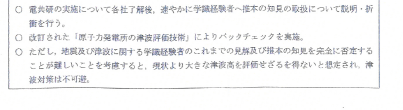
長期評価対策の先送り、「経営判断だった」
政府の地震調査研究推進本部(地震本部)が2002年に発表した長期評価「福島沖の日本海溝沿いでも津波地震が起きうる(高さ15.7m)」という予測について、金戸氏も、高尾氏、酒井氏と同様に「取り入れずに耐震バックチェックを通すことは出来ないと思っていた」と、はっきり証言した。
「地震本部という国のトップの組織があって、著名な地震の研究者が集まってまとめた長期評価を、取り入れずに(耐震バックチェクの)審査を通すことはできない」という理由だった。「絶対に起きるものとは言えないが、否定はできないもの」と考えていたという。
金戸氏は、2007年11月1日に、東電設計の久保賀也氏(第4回公判の証人)から「(長期評価を)取り入れないとまずいんじゃないでしょうかとアドバイスをもらった」と述べた。東通原発の設置許可申請で長期評価の考え方を取り入れて地震の揺れを想定していたことから、津波で長期評価を取り入れないと、「東電として矛盾が生じる」という理由だった。
2008年7月31日の武藤元副社長との会合までは、「長期評価を取り入れて耐震バックチェックを進める、対策として沖合防波堤と4m盤への対策を進めていくこと、これを決めてもらえればと考えて準備していた」と証言。会合当日、武藤元副社長が長期評価を取り入れないことを決めた(いわゆる「ちゃぶ台返し」)ことについて「想像していなかった」、対策工事をしないことも「それも無いと思っていました」と述べた。
武藤氏の対応については「その対応は経営判断したと受け止めた」「時間は遅くなるけど、対策はやることになると思っていた」と話した。
会合当日すぐ、上司の酒井氏が日本原電や東北電力に会合の様子を伝えたメールを送信していたことについて「180度変わった結論になったので、早く伝えなければとメールしたのだろう」と説明した。
「外に漏れ出すと説明しづらい資料」
「ちゃぶ台返し」の後、同年9月8日に酒井氏が高尾氏、金戸氏にメールを送っていた。「最終的に平成14年バックチェックベース(改造不要)で乗り切れる可能性は無く、数年後には(どのような形かはともかく)推本津波をプラクティス化して対応をはかる必要がある」。
これについて、金戸氏は「(武藤氏の指示にしたがって土木学会で)長期評価の波源を福島沖に置くか研究を実施しても、何も対策をしなくても良いという結果にはならない。対策をいずれやらないといけないという意味だった」と説明。酒井氏と同様、時間稼ぎという認識があったようにみえる。
9月10日には、福島第一原発の現地で、所長ら18人と、本店の関係者で「耐震バックチェック説明会」が開かれた。この際の資料[1]を金戸氏は作成。酒井氏からは「真実を記載して資料回収」と指示され、資料には「津波対策は不可避」と書いた。議事メモ[2]には「津波に対する検討状況(機微情報のため資料は回収、議事メモには記載しない)と書かれていた。
金戸氏は「外に漏れ出すと説明しづらい資料なので」と、これらの文言について説明した。「土木学会で3年かけて研究、すぐには対策に着手しない」という東電のやり方に、社会に対して説明できない、後ろめたいものを自覚していたのではないだろうか。
「解決困難でもやめないこと」怒ったセンター長
その後も、土木調査グループのメンバーは、「土木学会における検討結果が得られた時点(2012年)で、対策工事が完了していることが望ましい」という考えだったが、対策は進まなかった。「なんで早く進まないのか、フラストレーションがたまった」と証言した。
2010年8月には、津波の想定、対策に関わる部署(土木調査グループ(G)、機器耐震技術G、建築耐震Gなど)を集めて「福島地点津波対策ワーキング」がようやく発足した。
しかし、ワーキング発足の後も、「機器配管が濫立しており、非常用海水ポンプのみを収容する建屋の設置は困難」(建築耐震G)など悲観的な報告が続くばかりだった。「解決困難でも止めないことと、土方さん[3]は怒っていました」と述べた。
「15.7m対策では事故は防げなかった」への疑問
2011年3月11日。前月に東通原発の事務所に異動になっていた金戸氏は、青森県の三沢空港にいるときに地震に遭遇した。
「長期評価の見解を考慮した津波は、南東から遡上してくる。今回の津波は遡上してくるパターンが全然違っていた。ちょっと違いすぎる。長期評価の対策をしていたからといって今回の事故が防げたとは思えない」と金戸氏は証言した。
これには、いくつか疑問がある。
一つは、15.7mの津波対策として、金戸氏の頭にあった沖合防波堤や4m盤対策だけでは不十分で、審査を通らなかった可能性があることだ。耐震バックチェックで津波分野を担当していた今村文彦・東北大教授は、「15.7m対策には、1号機から4号機の建屋前(10m盤)にある程度の高さの防潮壁が必要で、それがあれば311の津波もかなり止められただろう」と述べている(第15回公判)。
もう一つは、運転しながら対策工事をすることが認められず、311前に運転停止に追い込まれていた可能性があることだ。東電の経営陣は、対策工事の費用より、さらに経営ダメージが大きい運転停止を恐れ、研究名目で時間を稼ごうとしたのではないだろうか。
防波堤などの対策工事は目立つから、着手する段階で、新しい津波想定の高さを公表する必要がある。しかし従来の津波想定(5.7m、外部に公開されていたのは3.1m)を、一気に15.7mに引き上げるとアナウンスした時、地元は運転継続しながらの工事を認めない可能性があった。その場合、福島第一は3月11日には冷温停止していたことになり、大事故にはつながらなかった。
長期評価より重い貞観リスク
渋村弁護士は貞観地震の問題についても尋ねた。
「貞観を取り入れなくて良いと考えていたのか」
金戸氏「長期評価と同じように、研究してからとりこもうと考えていた」
長期評価の15.7mは、記録には残っていないが、地震学の知見から予測される「想定津波」だ。一方、貞観津波タイプは、過去に何度も襲来した実績のある「既往津波」である。より確度は高い。450年から800年周期で福島県沿岸を襲っており、前回は1500年ごろに発生していたから[4]、周期からみると切迫性さえあった。
だから、「15.7m」と「貞観タイプ」では、原発へのリスクを考える時には重みが違う。同様に扱うとした金戸氏の答えは、疑わしい。
おまけに、お隣の女川原発はすでに貞観タイプを想定して報告書を原子力安全・保安院に提出ずみだった。女川と同じ貞観タイプの波源を想定すると、福島第一は4m盤の非常用ポンプが運転不能になることもわかっていた。
2011年4月には、地震本部の長期評価改訂版が公表される予定だった(第11回、島崎邦彦・東大名誉教授の証言参照)。2002年版と同じ津波地震(15.7m)に加え、貞観タイプへの警告も新たに加わっていた。この時点で運転停止に追い込まれるリスクを警戒していたからこそ、東電は文部科学省に長期評価の書き換えまでさせたのではないだろうか[5]。
[1] 東電株主代表訴訟の丙90号証の2
[2] 甲A100
[3] 土方勝一郎・原子力設備管理部新潟県中越沖地震対策センター長、酒井氏の上司
[4] 産業技術総合研究所 活断層・地震研究センター AFERC NEWS No.16 2010年8月号
https://unit.aist.go.jp/ievg/katsudo/ievg_news/aferc_news/no.16.pdf
[5] http://media-risk.cocolog-nifty.com/soeda/2014/01/post-c88c.html
橋本学・島崎邦彦・鷺谷威「2011年3月3日の地震調査研究推進本部事務局と電力事業者による日本海溝の長期評価に関する情報連絡会の経緯と問題点」日本地震学会モノグラフ「日本の原子力発電と地球科学」2015年3月、p.34



-390x220.jpg)