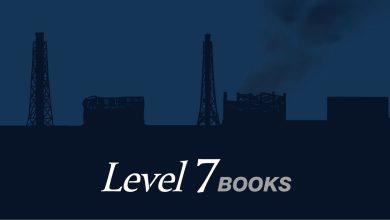東京電力福島第一原発事故を起こした刑事責任を問われ、強制起訴された東電の旧経営陣の無罪が2025年3月5日、確定した。最高裁判所第二小法廷(岡村和美裁判長)は、旧経営陣を無罪とした一審東京地裁、二審東京高裁の判断を支持し、上告を棄却した。
この裁判では、巨大な科学技術の利用と、その安全対策の兼ね合いの責任が問われた。不確実さを必ず伴う地震の予測を、経営者は安全対策にどう反映すべきかが大きな争点だったが、最高裁は明確な考え方を示さないまま刑事裁判を終結させた。最高裁がこんな逃げ腰では、科学技術が引き起こすかもしれない将来の大災害を裁判で防ぐことはできないだろう。
地震本部の長期評価、「現実的な可能性ない」
政府の地震調査研究推進本部(地震本部)は2002年7月に、福島第一原発の東約200キロの海底にあるプレート境界(日本海溝)で、マグニチュード(M)8.2程度の大地震が発生しうると予測(長期評価)した。この地震は高さ15.7mの津波を引き起こし、福島第一の敷地高さ10mを超えるという計算結果を、東電の旧経営陣は知っていた。
最高裁の決定[1]は、この長期評価についてこう判断を示した。
「長期評価の見解は、10m盤を超える津波が襲来するという現実的な可能性を認識させるような性質を備えた情報であったとまでは認められず、被告人らにおいても、そうした現実的な可能性を認識していたとは認められないとの原判決の判断が合理性を欠くものと考えるのは困難である」
政府の機関が公表した地震予測なのに、「現実的な可能性がない」と切り捨てたのだ。
「現実的な可能性」の定義を明らかにしなかった最高裁
問題は、原審の東京高裁や最高裁が、「現実的」という言葉の意味を明確にしていないことだ。指定弁護士は、上告趣意書[2](p.77)の中でこう述べている。
結果発生についての注意義務違反を問う過失犯については、結果発生についての予見可能性ないし予見義務と回避可能性ないし回避義務が要求される。
予見可能性については、「具体的予見可能性説」と「危惧感説」の対立がある。
通説・判例は、「具体的予見可能性説」を採っていると言われている。
ところが、原判決は、本件原子力発電所に10m盤を超える津波が襲来することについての「現実的な可能性」があると認識することを問題にしている。
「現実的」という言葉は、「具体的」という言葉とは明らかに異なる意味合いを持つところ、原判決において「現実的」という言葉の内容は明確にされていない。「現実的な可能性」という言葉が、10m盤を超える高さの津波の「切迫性」や「確実性」を意味しているとすれば、これまでの「具体的な可能性」よりも、相当に程度の高い可能性を要求していることになる。
そうであれば、原判決は、被告人らの過失犯の成立の判断において、不当に高い予見可能性を要求する誤りを犯している。
切迫性をめぐっては、2018年4月27日の東京地裁の第一審第9回公判[3]で、証言台に立った津波想定担当の東電社員と裁判官の間でこんなやりとりがあった。
裁判官「早急に対策を取らないといけない雰囲気ではなかったのか」
東電社員「東海、東南海、南海地震のように切迫感のある公表内容ではなかったので、切迫感を持って考えていたわけではない」
裁判官「15.7mが現実的な数字と考えていたわけではないのか」
東電社員「原子力の場合、普通は起こり得ないと思うような、あまりに保守的なことも考えさせられている。本当は、起きても15mも無いんじゃないかとも考えていた」
どうも東京地裁の裁判官は、切迫性のある情報でなければ現実的でなく、責任を問えないと考えていたことがうかがえる。その考え方が最高裁まで踏襲されているようだ。
「自然災害の事故責任、問えなくなる」
しかし、地震の予測は非常に難しい。地震学者の纐纈一起・慶應義塾大学SFC研究所上席研究員はその要因を三つ挙げている[4]。
1)再現実験ができない
2)過去のデータを研究するにしても大規模地震発生の間隔が長すぎることなどから、分析対象となるデータが限られている。
3)地震は岩盤の破壊現象だから、その過程や結果を予測することが難しい。ガラスを割ったとき、どのように割れ、破片がどう飛び散るかを正確には予測できないのと同じ。
研究が進めば進むほど「単純な予測は困難」と研究者らは考えるようになってきているのに、最高裁は発生時期のかなり正確な予測(切迫性)まで求めているのである。
指定弁護士の上告趣意書はこう指摘している(p.86)。
津波の襲来が不確実であり、予測に限界があるとすると、本件原子力発電所に10m盤を超える津波が襲来することが、「切迫していること」「確実であること」を正確に知らせる情報はあり得ないのであって、そのような津波が襲来することを「現実的な可能性」として認識することは、何人にも期待できないことになる。
そうすると
① 津波の襲来に対しては、およそ予見可能性はあり得ないことになり
② 津波対策をしない事業者の責任は問えなくなり
③ 原子力発電所の安全性確保は弛緩する。
さらに言えば、自然災害に起因する事故についての過失責任はおよそ免責されることになる。
このような結論が、刑法理論としても正しいとは到底思われない。
指定弁護士の神山啓史弁護士は、高裁判決後の記者会見[5]で、「現実的な可能性」という言葉について、「自然災害から原子力発電所を守る時の注意義務として、このような(判決のような)考え方でいいのか、議論の余地がある。我々としては議論をもっともっと深めていきたい」と話していた。しかし最高裁は応じず、高裁判決の「現実的な可能性」というあいまいな言葉を吟味もせずなぞって上告を棄却しただけだった。
今回の最高裁の判断について、指定弁護士の石田省三郎弁護士は「令和4年に、同じ第二小法廷が示した判断とも矛盾する」と記者会見で指摘している。各地に避難した人たちが東電と国に損害賠償を求めた集団訴訟の判決(22年6月17日)で、最高裁は国の責任を認めなかったものの、長期評価にもとづく津波計算について「安全性に十分配慮して余裕を持たせ、当時考えられる最悪の事態に対応したものとして、合理性を有する試算であった」としていたからだ。
「最高裁判所の見解が支離滅裂になっているのではないか」と石田弁護士は言う。
株主代表訴訟の高裁判決(6月6日)に注目
業務上過失致死傷などの容疑で旧経営陣らが告訴・告発されたのは13年前の2012年6月。その後、東京地検は、勝俣恒久元会長らを2度不起訴にしたが、市民による東京第五検察審査会がそれを2度とも「起訴すべきだ」とひっくり返し、公開の刑事裁判が始まった。
2017年から始まった公判では、東電社員だけでなく、規制側の旧経済産業省原子力安全・保安院の職員、研究者らが証言し、東電と他の電力会社がやりとりしていた電子メール、非公開会合の議事録なども大量に公開された。これらを読み解くことで、なぜ事故を防げなかったのか、組織の動きが見えた。
刑事責任を問う裁判とは別に、東電の旧経営陣の責任を追及した株主代表訴訟では、東京地裁(朝倉佳秀裁判長)は22年7月に、「津波は予見できて事故は避けられた」として、今回刑事裁判で無罪が確定した元副社長2人を含む4人の旧経営陣に、13兆円を超える支払いを命じている。
株主訴訟の株主側弁護団の河合弘之弁護士は、3月6日の会見でこう述べた。
「刑事裁判の一審、二審を通じて出てきた証拠によって、株主代表訴訟の立証を充実させることができた。株主代表訴訟の一審判決は、刑事事件の証拠がなければ不可能だったと思う。刑事告訴は、重要な歴史的な意味があった。私たちが頑張らなければ、事故の真実は歴史の闇の中に、葬られたと思う。残念な結果にはなったが、白日の下に色々な事実を晒すことができた。国民の所産となる」
6月6日に、株主代表訴訟の東京高裁判決がある。地震予測の不確実さの扱いをどう判断するのか、注目したい。
[1] https://shien-dan.org/wp-content/uploads/20250306-doc.pdf
[2] https://shien-dan.org/wp-content/uploads/20230913_shien-dan_doc.pdf
[3] https://level7online.jp/2018/%E7%AC%AC9%E5%9B%9E%E5%85%AC%E5%88%A4%E5%82%8D%E8%81%B4%E8%A8%98/
[4] 通販生活2025年3・4月号p.14 纐纈一起「地震の予測は非常に難しい。90年代以降に起きた大地震の約7割が「想定外」でした」
[5] https://level7online.jp/2023/20230123/
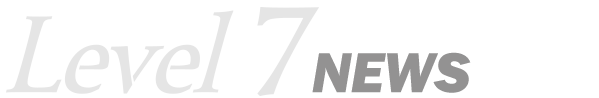

-390x220.jpg)